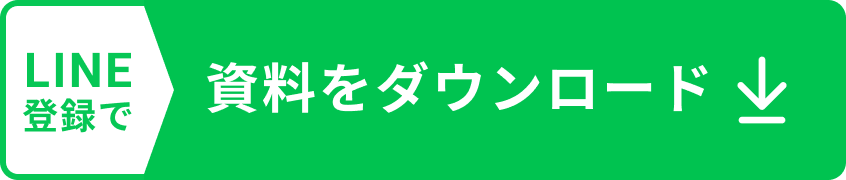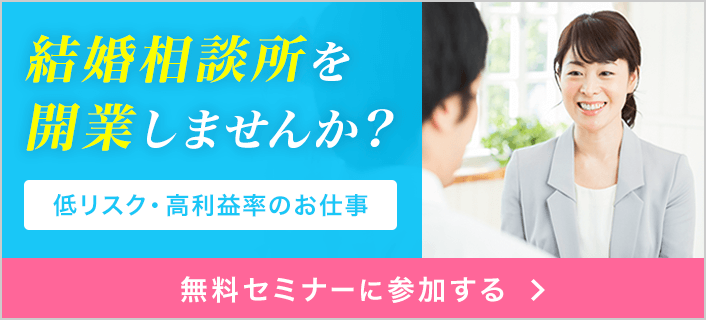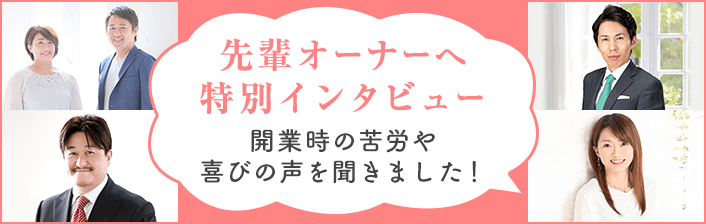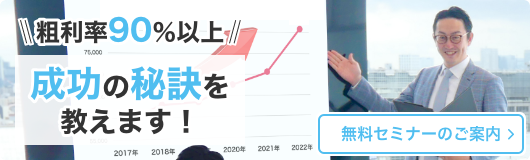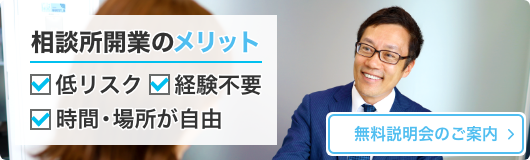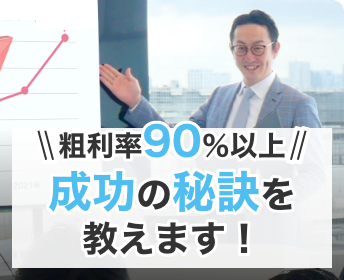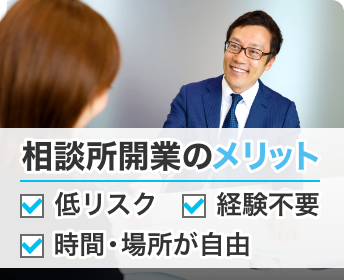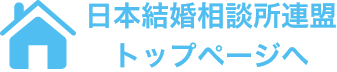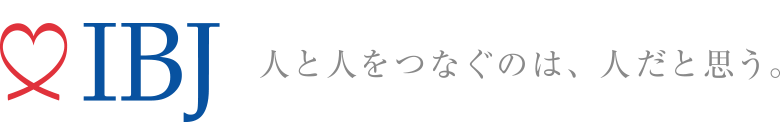近年、専業主婦から共働きとして主婦の方が働きに出る機会が多くなっています。
専業主婦と言えば女性だった時代から、今では専業主夫という男性が家事や育児を行うという家庭も出てきているようです。厚生労働省の発表によると、1980年には専業主婦の世帯が1,100万世帯あった頃に比べ、2017年には641万世帯、共働きの世帯が1,180万世帯以上になっているようです。
ただ、平成29年の就業構造基本調査では、既婚の女性就業者のうち正規職員として働いているのは約30%にとどまり、約55%はパートなどの非正規職員です。家事や育児と両立するために非正規で働くことを選んでいる方も多いと思いますが、家事や育児と両立できるのであれば、起業してみたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事実、既婚の女性起業者は約768,000人いるそうです。
今回は、起業したい主婦のための成功のポイントとおすすめの仕事をご紹介していきます。
起業したい主婦のための成功のポイント

そもそも、主婦が起業をするというのは可能でしょうか?
「家事や育児があってフルタイムで働くことも難しいのに、起業なんて…」と思うかもしれません。ハードルが高いと感じる理由として、「時間がない」「資金がない」「見込み客がいない」「起業のノウハウがない」といった理由が挙げられると思います。
主婦が起業して成功するためのポイントは、上記の「ない」を無理に作ろうとするのではなく、ないことを前提として事業を組み立てることです。
時間がない→スキマ時間を利用する
主婦が仕事をするのが難しいのは、「平日9時から17時まで」というような連続した時間を確保することが難しいためです。そうであれば、スキマ時間を使って起業できないか考えてみましょう。
家族の協力が得られる夜間や休日を使ってできる仕事や細切れ時間を使って進められる仕事、予約した時間にお客さんに来てもらうような仕事であれば、連続した時間を確保できない主婦の方でも起業することができるでしょう。
資金がない→費用がかからない仕事を選ぶ
起業のための資金が用意できないという方も多いと思います。女性が起業する場合、日本政策金融公庫が通常よりも低利で融資してくれる「女性、若者/シニア起業家支援資金」を利用することができますが、そもそも費用がかからない仕事を選ぶという選択肢もあります。
例えば、PCやスマホがあればできるような仕事であれば、新たに購入したとしても10万円くらいでしょうし、自宅でできる仕事やお客さんのところに訪問する仕事であれば、事務所や店舗を借りる必要がないので、追加費用がかかりません。また、仕入れが不要な仕事であれば、在庫を抱える必要がないため、リスクを下げることができます。
見込み客がいない→集客を支援してくれるサービスを使う
起業にあたっては、どうやって集客するかも悩みの種です。この悩みに対しては、集客を支援してくれるサービスを使ってみましょう。
仕事を発注したい人と仕事を受注したい人をマッチングさせるサービスや、講師と受講生をマッチングさせるサービス、ハンドメイド雑貨の販売プラットフォームなど、現在ではインターネットを利用したサービスが多数あります。こうしたサービスを利用すれば、顧客を見つけやすくなります。
起業についてのノウハウがない→セミナーに参加する
起業にはマーケティングや会計の知識がある程度必要です。これまでそうしたノウハウを身に付けるチャンスがなかった人は、セミナーに参加してみるのもよいでしょう。託児サービスがあるセミナーもあり、子育て中の主婦でも参加しやすくなっています。
女性向け起業セミナーの探し方や活用法については、女性のための起業セミナーの上手な活用術で詳しく説明していますので、そちらもあわせてご覧ください。
主婦が起業を考えるときにおすすめしたい仕事

上記の成功のポイントをもとに、主婦におすすめの仕事をご紹介します。
結婚相談所
結婚相談所は、自宅でも開業できるため初期投資が少額で済み、ランニングコストもあまりかからないので、損益分岐点も低いです。会員に対するアドバイスには人生経験を活かすことができ、結婚難・少子化といった社会的課題の解決に貢献することもできます。
Webライター
自宅のPCを使って手軽に始められるお仕事で、資格がなくても取り組むことが可能です。クラウドソーシングサイトを利用して仕事を受注したり、インターネット経由でライターやデザイナーを募集している企業や個人に応募して、直接契約で報酬を得る方法もあります。特にWebライターは、紙媒体と異なり、取材を行わずに執筆できる案件が多いため、初心者でも始めやすいのが特徴です。
アフィリエイト
自分自身が商品を販売するのではなく、商品やサービスをおすすめして、紹介先で商品やサービスが売れたら報酬を受け取る仕組みです。自分のホームページやブログに集客し、さらに商品が売れるように宣伝しなければならないので、Webマーケティングの知識が必要となります。実際に商品やサービスが売れるまでは報酬が得られないのが難点ですが、PCとネット環境があれば、どこでもできる仕事です。
コンサルタント・コーチング
パソコン1つで起業できる業種として起業する人が多いのが、コンサルティング業やコーチング業です。これらのビジネスでは、SkypeやZoomといった遠隔で通話できるパソコンソフトを使えば、自宅に居ながら経営をすることができます。コンサルティングやコーチングのビジネスは、企業が抱える問題解決などのBtoB向けのものから、個人の英語学習やコミュニケーションスキルの改善といったBtoC向けのものまで幅広い活躍のチャンスがあります。
ハンドメイド雑貨等のネット販売
ネットショップでハンドメイドアクセサリーを売ったり、商品を仕入れて販売するサービスです。立ち上げ直後は在庫を抱えると負担が重くなるので、在庫を持たずに商品を販売できるドロップシッピングを利用したり、実際の販売は別の業者に任せて集客だけを担当するアフィリエイトで始め、ノウハウを蓄積するのもひとつの手です。
主婦が起業するなら考えておきたい税金と健康保険のこと

主婦が起業するときに考えておきたいのが、「どのくらい稼ぎたいか?」です。単に目標を設定するというだけでなく、これまで夫の扶養に入っていた主婦が起業する場合には、税金や健康保険の問題が絡んでくるためです。
主婦の起業と税金
まず税金については、妻の年間所得(売上-経費)が48万円以下であれば、配偶者控除が受けられ夫の所得から38万円が控除されて所得税が計算されます。年間所得が48万円を超え133万円までの場合は配偶者特別控除が受けられ、段階的に38万円から3万円が夫の所得から控除されます(いずれも夫の所得が900万円以下の場合)。そして、年間所得が133万円を超えると夫の所得控除はなくなります。
住民税の計算についても同様に、妻の年間所得に応じて33万円から3万円が夫の所得から控除され、133万円を超えると所得控除がなくなります。
つまり、妻の年間所得が増えるに従って夫が所得に対する税金が増えていくことになるのです。具体的な税額がいくらになるかは、夫の所得額や配偶者(特別)控除以外の控除によっても異なるため、一概に言えませんが、税額計算ができるサイトがあるので、一度確認してみるとよいでしょう。
主婦の起業と健康保険
次に、健康保険ですが、夫が会社員のときに被扶養者として健康保険に入ることができるのは、年間収入が130万円未満の場合です。この「年間収入」ですが、売上から経費を引いて計算します。ただ、税金を計算する際の経費と異なり、「所得を得るために必要と認められる経費に限り」差し引くことができるとされているため、注意が必要です。具体的には、減価償却費は経費として認められません。
上記の基準に照らして、被扶養者に該当しないとされた場合は、国民健康保険に入る必要があります。国民健康保険料は市区町村によって異なりますが、40歳以上の主婦だけが国民健康保険に入る場合で年間収入が130万円だと、年間の保険料は15万円前後です。年間収入が125万円だった場合と比較すると、収入が5万円増えても保険料が徴収される分、差し引きでは年間収入が125万円のほうが手元に残る金額が増えます。
主婦の起業と扶養手当
夫が勤務している職場によっては、扶養手当を支給している場合があります。扶養手当の支給基準は配偶者控除が適用される基準、または社会保険の被保険者となる基準とされているところがほとんどです。支給基準から外れると、扶養手当の分だけ夫の収入が減ります。
これまで見たように、主婦が起業する場合、年間所得で130万円、つまり月の利益が10万円を超えるかどうかで様々な面で違いが生じてきます。家計全体に影響を与えるので、家族とよく相談するようにしましょう。
主婦で起業するなら低リスクで始められるビジネスを選ぼう

今回は、起業したい主婦のための成功のポイントとおすすめの仕事をご紹介してきました。
主婦が起業する場合、十分な時間が確保できなかったり、資金が少なかったりとハードルが高く感じるところもありますが、短時間・小資金で始められるビジネスを選ぶことで、低リスクで起業することができます。専業主婦の場合、生活費については夫を頼ることができるので、気持ちの上では楽に始められます。
起業に伴うリスクを回避するには、低リスクで始められる事業を選ぶことが重要です。結婚相談所は店舗が不要かつ1人でも始められる事業のため、低リスクでの開業が可能です。IBJでは、低リスクで開業できる「結婚相談所」の無料相談会を実施しております。結婚相談所のビジネスモデルについて些細な疑問にも丁寧にお答えしますので、ぜひお気軽にお申込みください。
無料相談会のお申込みはこちらから≫